50��̎����ԕی��̕ی����̑���́H�q�ǂ����^�]����ꍇ�̒��ӓ_������I - SBI���ۂ̎����ԕی�
50��̎����ԕی��̕ی����̑���́H�q�ǂ����^�]����ꍇ�̒��ӓ_������I
![50��̎����ԕی��̕ی����̑���́H�q�ǂ����^�]����ꍇ�̒��ӓ_������I](/car/column/images/img_carColumn99--01.jpg)
�����ԕی��̕ی����͂��܂��܂ȗv�f����Ɍ��߂��܂����A���̈���L����ی��҂́u�N��v�ł��B���Ƃ���50��̕����L����ی��҂ɂȂ�ꍇ�A��ʓI�ɂ͂ǂ̂��炢�̕ی����ɂȂ�̂ł��傤���B
�{�L���ł͔N��ʂ̎����ԕی��̕ی�������ƁA50�オ�ق��̔N��Ɣ�ׂĕی����������̂��E�Ⴂ�̂��ɂ��ĉ�����܂��B�܂��q�ǂ����^�]����悤�ɂȂ����ꍇ�̒��ӓ_�ƁA�ی����̐ߖ���@�ɂ��Ă�������Ă��܂��B���N��̐l�������炭�炢�����ԕی��̕ی������Ă���̂��m�肽���Ƃ����l��A�q�ǂ����^�]�Ƌ����擾�����Ƃ����l�Ȃǂ́A���ЎQ�l�ɂ��Ă��������B
�ڎ�
�y�N��ʁz�����ԕی��̕��ϕی���
50���10��E20��Ȃǂ̎�҂�A70��ȏ�̍���҂Ɣ�ׂĕی������ꂪ�Ⴂ�X��������܂��B
�N��ɂ���Ď����ԕی��̕ی����͂ǂ̂悤�ɕς���Ă���̂ł��傤���B��Ƃ���SBI���ۂ̎����ԕی��̕ی��������Ă݂܂��傤�B�N��ʂɌ��������ԕی��̔N���ی����̕��ς͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
| �N�� | �ԗ��ی����� | �ԗ��ی��Ȃ� |
|---|---|---|
| 20�� | 69,925�~ | 43,756�~ |
| 30�� | 47,316�~ | 27,468�~ |
| 40�� | 44,351�~ | 24,689�~ |
| 50�� | 45,375�~ | 23,879�~ |
���ی��n����2021�N1������12���ŁA���Ђ���SBI���ۂ̎����ԕی��ɐV�K�ł��_�ꂽ�L����ی��҂��܂̃f�[�^���W�v���ĎZ�o�B�i2022�N12��12�����_�j
�\������ƁA20��E30�����40��E50��̕ی������Ⴍ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�܂��ԗ��ی��Ȃ��̏ꍇ�́A50�オ�ł����ϕی������Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B
50��̎����ԕی��̕ی������ꂪ�Ⴂ���R

50��̎����ԕی��̕ی������ꂪ�A�ق��̔N��Ɣ�ׂĒႢ�X���Ȃ̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤���B��ȗ��R�Ƃ��āu���̗��v�u�m���t���[�g�����v��2�̗v�f������܂��B���ꂼ��ǂ̂悤�ɕی�������̒Ⴓ�ƊW���Ă���̂��A�ȉ��ɏڂ���������܂��B
���̗����Ⴂ�l�⍂��҂Ɣ�ׂĒႢ����
50��̎����ԕی��̕ی������ꂪ�Ⴍ�Ȃ��̗��R�́A��ʎ��̂���������m���i�ȉ��u���̗��v�Ƃ����܂��j�̒Ⴓ�ł��B
���̗����Ⴂ�قǁA�ی�������͒Ⴍ�Ȃ�X��������܂��B50���10��E20��̎�҂�70��ȏ�̍���҂Ɣ�ׂČ�ʎ��̂̔������������Ȃ��X�������邽�߁A�ی������ꂪ�Ⴍ�Ȃ�̂ł��B
�x�@���́u���H�̌�ʂɊւ��铝�v�v�ɂ��ƁA�N��w�ʂ̖Ƌ��ۗL��10���l������̌�ʎ��̌����i�ߘa4�N�j�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
| �N��w | ��ʎ��̌����i���j |
|---|---|
| 20�`24�� | 597.2 |
| 25�`29�� | 414.8 |
| 30�`34�� | 320.2 |
| 35�`39�� | 290.6 |
| 40�`44�� | 282.2 |
| 45�`49�� | 290.7 |
| 50�`54�� | 296.1 |
| 55�`59�� | 295.9 |
| 60�`64�� | 295.7 |
| 65�`69�� | 299.1 |
| 70�`74�� | 341.0 |
| 75�`79�� | 372.1 |
�o�T:�u�ߘa�S�N���̌�ʎ��̂̔����v(�x�@��)
(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001020602&cycle=7&year=20220)
�\�ɂ���50��͂������300�������ŁA20���菭�Ȃ������ł��B70����74�́u341.0���v�Ə��������Ȃ�A�N��w���オ��ɂ�Č���������ɑ����Ă����܂��B
50��̎��̗����Ⴂ���R�Ƃ��ẮA��҂Ɣ�ׂĉ^�]�o�����L�x�ȃh���C�o�[�������A10��E20��̂悤�ɖ����ȉ^�]������l�����Ȃ����Ƃ��l�����܂��B�܂���荂��ɂȂ�ƔF�m�@�\�̒ቺ�ɂ���Ď��̂��������₷���Ȃ�X���ɂ���܂��B
���̂悤�Ɏ�ҁE����҂Ɍ����鎖�̗��������Ȃ�v�f��50��ł͏��Ȃ����Ƃ���A�ی������ꂪ�Ⴍ�Ȃ�̂ł��B
�m���t���[�g�����������l�������X���ɂ��邩��
������̗��R�́A50��͎����Ԃɏ��n�߂Ă��琔�\�N���o�߂��Ă���x�e�����h���C�o�[�������A20�����A�������͂���ɋ߂�������ێ����Ă���l�������X���ɂ���_�ł��B
�m���t���[�g�����Ƃ́A�����ԕی��̌_��ɓK�p����銄���E�������̓����敪�̂��Ƃł��B�_��҂����L�E�g�p����Ԃ̌_��䐔�����Ђ��܂�9��ȉ��̏ꍇ�ɓK�p����܂��B��{�I�ɁA�m���t���[�g�����������Ȃ�قǕی����̊������������Ȃ�܂��B
1�N�Ԃ̕ی����Ԃ�ʂ��Ė����̂̏ꍇ�A�_����X�V����ƃm���t���[�g������1�オ�邵���݂ł��B�����̂��p���ł���A���߂Ď����ԕی��ɉ������Ă���14�N�ōō���20�����ɓ��B���܂��B
20��ł́A��������e�̓����������p���Ȃǂ��Ȃ����20�����ɓ��B���邱�Ƃ͕s�\�ł��B���̂���20��Ȃǂ̎�҂Ɣ�ׂ�50��̕��̕ی������ꂪ�Ⴍ�Ȃ�̂ł��B
�Ȃ��A�����̈����p���ɂ��ďڂ����͎��̏͂ʼn�����܂��B
�q�ǂ����^�]����悤�ɂȂ���50��̐e���m���Ă��������ی����̐ߖ���@�Ƃ́H
![�q�ǂ����^�]����悤�ɂȂ���50��̐e���m���Ă��������ی����̐ߖ���@�Ƃ́H](/car/column/images/img_carColumn99--03.jpg)
50��ɂȂ�Ǝq�ǂ��������Ԃ̉^�]�Ƌ����擾���A�^�]����悤�ɂȂ�P�[�X�������Ȃ�ł��傤�B�q�ǂ����^�]����悤�ɂȂ�ƁA�e�̎����ԕی��̕ی����������Ȃ邱�Ƃ����邽�ߒ��ӂ��K�v�ł��B�q�ǂ����^�]����悤�ɂȂ����e���m���Ă��������ی����̐ߖ���@�ɂ��āA�ȉ��ɉ�����܂��B
�N������͂��ł��ύX�ł���
�����̎q�ǂ����^�]����悤�ɂȂ邱�Ƃɂ��A�e�̕ی����������Ȃ�v����1�Ƃ��āA�N�����������܂��B�N������Ƃ́A�u21�Έȏ�⏞�v�ȂǕ⏞����^�]�҂͈̔͂�N��Ō��肷�邱�ƂŁA���̊��������邵���݂̂��ƁB�N��͈̔͂��L���Ȃ�قǁA���������Ⴍ�Ȃ�A�ی����������Ȃ�܂��B
���݂̌_��Łu26�Έȏ�⏞�v�ȂǔN��������������Ă���ꍇ�A�q�ǂ����^�]����悤�ɂȂ�ƁA�q�ǂ��̔N��ɍ��킹�āu�N����킸�⏞�v�ȂǔN������͈̔͂��L����K�v������ł��傤�B���̂��ߕی����������Ȃ�ꍇ������̂ł��B
�ی�����ߖ邽�߂ɂ́A����I�ɔN����������������Ƃ��������߂��܂��B���Ɏq�ǂ��̔N��オ����21�A26�ȂǔN�������ύX�ł���N��ɒB�����ۂɂ́A�������ɂ���ĕی����������ł���ł��傤�B�N������͕ی��̍X�V�^�C�~���O�ɊW�Ȃ��A���ł��ύX�ł���̂ŁA�N��ς�����炷���ɂł������������܂��傤�B
�^�]�Ҍ�������t����Εی����̊���������
�ی�����ߖ������̕��@�́u�^�]�Ҍ������v�̗��p�ł��B
�^�]�Ҍ������Ƃ́A�_���Ԃ��^�]����l�����肷�邱�Ƃɂ��A�K�p�����ی����������������̂��Ƃł��B�ی���Ђɂ���ċ敪�͈قȂ�܂����ASBI���ۂł͈ȉ�3�̋敪������܂��B
| �^�]�Ҍ���̋敪 | �⏞�̑ΏۂƂȂ�^�]�� |
|---|---|
| �^�]�Җ{�l���� | a�̂� |
| �^�]�Җ{�l�E�z��Ҍ��� | a�����b�̂� |
| �^�]�҉Ƒ����� | a�Eb�Ec�Ed |
-
a�F�L����ی���
-
b�Fa�̔z���
-
c�Fa�܂���b�̓����̐e��
-
d�Fa�܂���b�̕ʋ��̖����̎q
�⏞�̑ΏۂƂȂ�^�]�҂͈̔͂������Ȃ�قǁA�ی����͈����Ȃ邵���݂ł��B���̂��߁A���Ƃ��Ύq�ǂ��������̎����Ԃ������Ă���ȂǁA��{�I�ɐe�̎����Ԃɏ��Ȃ��ꍇ�́u�^�]�Җ{�l�E�z��Ҍ���v�u�^�]�Җ{�l����v�ɂ��邱�Ƃŕی�����ߖ�ł��܂��B
1���P�ʂʼn����ł��鎩���ԕی�������
�q�ǂ����N�ɐ���قǂ����^�]���Ȃ��̂ł���A�u1���P�ʂʼn����ł��鎩���ԕی��v�����p���邱�Ƃŕی�����ߖ�ł��邩������܂���B
���i�͑O�q�́u�N������v��u�^�]�Ҍ������v�Ŏq�ǂ���⏞�̑ΏۊO�Ƃ��ĕی����������}���A�q�ǂ����^�]����Ƃ������u1���P�ʂʼn����ł��鎩���ԕی��v�𗘗p���Ďq�ǂ��̕⏞���m�ۂ���Ƃ������@�ł��B
1���P�ʂʼn����ł��鎩���ԕی��Ƃ́A24���ԒP�ʂŕ⏞��ݒ�ł��A�K�v�ȓ��������p�ł��鎩���ԕی��̂��ƁB���܂����p����ΐe�̎����ԕی��̕⏞�ΏۂɎq�ǂ����܂߂�����ی�����ߖ�ł���\��������܂��B
�ی�����ߖ�ł��邩�ǂ����́A�q�ǂ����^�]����p�x�ɂ���Ă��ς���Ă��܂��B�ڂ������ς�����Ĕ�r���A�ǂ��炪�����Ȃ邩�������܂��傤�B
�q�ǂ��ɓ����������p���A�q�ǂ��������ی������Ⴍ�Ȃ�
�q�ǂ��Ɂu�����̈����p���v�����邱�ƂŎq�ǂ��̕ی����������Ȃ�A�ƌv�S�̂ł̕ی�����ߖ�ł��邱�Ƃ�����܂��B
�����̈����p���Ƃ́A�L����ی��҂�ύX����ۂȂǂɃm���t���[�g�����������p�����Ƃł��B�L����ی��҂�e����q�ǂ��ɕύX����ۂɁA�e�̃m���t���[�g�������q�ǂ��Ɉ����p����ꍇ������܂��B�e�̍����m���t���[�g�������q�ǂ��Ɉ����p���ł���A�q�ǂ��̕ی�����ߖ邱�Ƃ��\�ł��B
�q�ǂ��ɓ����������p������A�e���������������ԕی��ɉ�������ꍇ�A�e�̓����͒ʏ�6��������̃X�^�[�g�ƂȂ�A����܂ł��ی����������Ȃ��Ă��܂��܂��B���������łɉ�������Ƃ���50��͎q�ǂ��̔N������ی����������Ȃ邱�Ƃ������A�g�[�^���ł͐ߖ�ɂȂ�ꍇ������܂��B
�������u�ʋ��̎q�ǂ��v�ɓ����̈��p�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����ߒ��ӂ��Ă��������B
�܂������̈����p���ɂ���ĕی�����ߖ�ɂ́A�e�̓�����7�����ȏ�ł���K�v������܂��B�m���t���[�g������6��������X�^�[�g���邽�߁A6�����ȉ��̓����������p���ł��ߖ�ɂȂ�Ȃ����߂ł��B
�܂Ƃ�
50��̎����ԕی��̕ی�������́A�ق��̔N��Ɣ�r���ĒႢ�X��������܂��B������10�ォ��20��̎q�ǂ����^�]�Ƌ����擾���Ď����Ԃ��^�]����悤�ɂȂ�ƁA�ی����������Ȃ�ꍇ�������A���ӂ��K�v�ł��B�{�L���ŏЉ���ی����̐ߖ���@���悭�������A�������œK�Ȏ����ԕی���I�т܂��傤�B
SBI���ۂ̎����ԕی��́A�C���^�[�l�b�g����̐V�K���\���݂Ȃ�ی���14,500�~�i��1�j�������ɂȂ�܂��B���Љ���u�N������v�u�^�]�Ҍ������v���ݒ�ł��A�ɍ��킹���_����e�E�ی����ɂȂ�悤�������������܂��B�����������Ȃ����łȂ��A�ƊE�ō������i��2�j�̃��[�h�T�[�r�X�����ׂĂ̂��_��ɖ����ŕt���Ă��܂��B������̍ۂ����S�ł��鎩���ԕی��Ƃ��Ă��Ђ��������������B
-
��1�@�C���^�[�l�b�g�����i14,000�~�j�A�،��s���s�����i500�~�j��K�p���������z�ł��B�����̏ꍇ�͔N��14,520�~�i�@14,040�~�A480�~�j�ƂȂ�܂��B
-
��22025�N7��SBI���ے��ׁB�e�Ђ̖������[�h�T�[�r�X�̔�r�\���������B
���M�N�����F2023�N9��25��
�֘A�R����

�����̕����Љ�l�ɂȂ肽�Ă�20��B�ʋȂǂ̂��߂Ɏ����Ԃ��K�v�ɂȂ�A�����ԕی������߂Č����������������Ǝv���܂��B����́A20��E���߂Ă̎����ԕی��ł��Ȃ�ׂ��ی�����}����R�c�ɂ��Ă��Љ�܂��B
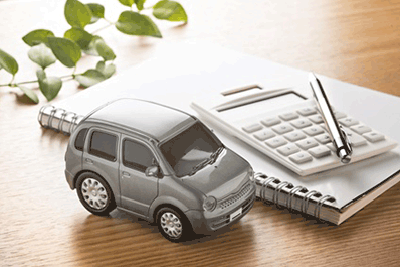
�����ӕی��́A�����Ԏ��̂̔�Q�҂̋~�ς�ړI�Ƃ��Ă���ی��ł��B���̂��߁A�����Ԃ�o�^����ہA�Ԍ���ʂ��ۂɉ������`���t�����Ă��܂��B���̂̑���̎��S�A�����A����Q�Ȃǂ͕⏞�Ώۂł����A����̎Ԃ╨�ɑ��Q��^�����ꍇ�̏C����p�A�������g�̂����̎��Ô�Ȃǂ͕⏞����܂���B

�����ԕی��̍X�V���ɕی����������ƈ����ł��Ȃ��������������͑����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�N������v�͕ی�����ߖ�|�C���g��1�ł��B�N������Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ŁA���ۂɂǂ̂悤�ȏ�ʂŗ��p�ł��A���̒��ӓ_�͉����A�Ȃǂ����`�����܂��B

�ƒ����2��ڂ̎����Ԃ��w�����邱�ƂɂȂ����ꍇ�A�����ԕی���V���Ɍ_�邱�ƂɂȂ�ł��傤�B���̍ہu�Z�J���h�J�[�����v��K�p���邱�ƂŁA�����ԕی��̕ی�����ߖ�ł���ꍇ������܂��B�{�L���ł́u�Z�J���h�J�[�����Ƃ͉����v�Ƃ�����{����A�K�p���邽�߂ɖ������ׂ�������������܂��B

���ƂŎԂ𗘗p����o�c�ҁi�S���ҁj�̕��̒��ɂ́A�@�l�����̎����ԕی��̑����m�肽���Ƃ�������A�����ɎЗp�Ԃ̎����ԕی��ɉ����������Ƃ�����������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�{�L���́A�@�l���������ԕی��̑����A���g�N�ɉ���������@�ɂ��ĉ�����܂��B
�֘A�R����
-

20��̎����ԕی��̑I�ѕ��`�����ł����g�N�Ɏ����ԕی���������R�c�I�`
�����̕����Љ�l�ɂȂ肽�Ă�20��B�ʋȂǂ̂��߂Ɏ����Ԃ��K�v�ɂȂ�A�����ԕی������߂Č����������������Ǝv���܂��B����́A20��E���߂Ă̎����ԕی��ł��Ȃ�ׂ��ی�����}����R�c�ɂ��Ă��Љ�܂��B
-
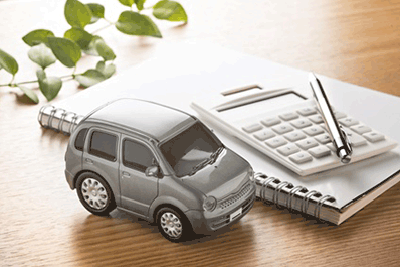
�C�ӕی��Ƃ́H�⏞�̎�ނ��������ۂ̃|�C���g�����
�����ӕی��́A�����Ԏ��̂̔�Q�҂̋~�ς�ړI�Ƃ��Ă���ی��ł��B���̂��߁A�����Ԃ�o�^����ہA�Ԍ���ʂ��ۂɉ������`���t�����Ă��܂��B���̂̑���̎��S�A�����A����Q�Ȃǂ͕⏞�Ώۂł����A����̎Ԃ╨�ɑ��Q��^�����ꍇ�̏C����p�A�������g�̂����̎��Ô�Ȃǂ͕⏞����܂���B
-

�����ԕی��̔N������Ƃ́H�N��敪��ߖ���@�����
�����ԕی��̍X�V���ɕی����������ƈ����ł��Ȃ��������������͑����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�N������v�͕ی�����ߖ�|�C���g��1�ł��B�N������Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ŁA���ۂɂǂ̂悤�ȏ�ʂŗ��p�ł��A���̒��ӓ_�͉����A�Ȃǂ����`�����܂��B
-

�Z�J���h�J�[�����Ƃ́H�������邽�߂̏����ƌ_�̒��ӓ_������I
�ƒ����2��ڂ̎����Ԃ��w�����邱�ƂɂȂ����ꍇ�A�����ԕی���V���Ɍ_�邱�ƂɂȂ�ł��傤�B���̍ہu�Z�J���h�J�[�����v��K�p���邱�ƂŁA�����ԕی��̕ی�����ߖ�ł���ꍇ������܂��B�{�L���ł́u�Z�J���h�J�[�����Ƃ͉����v�Ƃ�����{����A�K�p���邽�߂ɖ������ׂ�������������܂��B
-

�@�l���������ԕی��̑���́H���g�N�Ȏ����ԕی��Ɖ������@������I
���ƂŎԂ𗘗p����o�c�ҁi�S���ҁj�̕��̒��ɂ́A�@�l�����̎����ԕی��̑����m�肽���Ƃ�������A�����ɎЗp�Ԃ̎����ԕی��ɉ����������Ƃ�����������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�{�L���́A�@�l���������ԕی��̑����A���g�N�ɉ���������@�ɂ��ĉ�����܂��B
- �֘A�y�[�W
-
�C���^�[�l�b�g�����
�V�K���\������
�����ԕی�����
14,500�~�����I�� -
��①�C���^�[�l�b�g�����i14,000�~�j②�،��s���s�����i500�~�j��K�p�����ꍇ�̊����z�ł��B�����͔N��14,520�~�i①14,040�~②480�~�j�ƂȂ�܂��B
- ���p���E���_����e�ύX
�Ȃǂ̂��葱��
�����ԕی��̂����ς�
- �V�K�ł����������������̕�
-
0800-8888-581
9:00�`18:00�i12/31�`1/3�������܂��j
2025�N8���@25-0230-12-023

